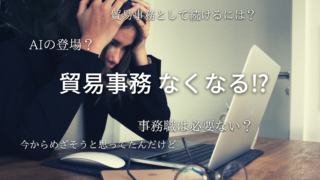こんにちは
有坂です。
今回は貿易事務をしていく上で大事なこと、
コミュニケーション
についてお話ししたいと思います。
以前に、このような質問を受けたことがあります。
・事務職だったらそんな人と面と向かって関わることないしコミュニケーションとか必要?
・あまり社交的じゃないから事務職がいいと思っているんだけど
事務職と聞くと社内で黙々と仕事をこなし、会話をするとしても社内の人、それも限られた人とだけ
といった風に想像される方もいるかもしれません。
実際に同じ事務職でも配属される部署の仕事内容によってはそうだったりします。
けれども、
貿易事務職の仕事は仕事を進めていく上で様々な人と関わります。
以前にも貿易事務のコミュニケーションに関して少し書いている記事がありますが
今回改めて「貿易事務とコミュニケーション」に関してお伝えできればと思います。
Contents
貿易事務は様々な人と関わる
貿易事務は事務職なので基本的には内勤であることが多いです。
営業職と異なり、どこか遠方に出張に行ったり近場であっても取引先などに出向くことはほとんどありません。
しかしながら1件の貨物を無事に目的地まで到着させるためには様々な人と関わります。
輸入時であれば
1、輸出元の企業
2、船会社、もしくは船会社の代理店
3、日本に到着した貨物を通関切れるまで保管しておく保税倉庫
4、通関の手配等々をしてくれる通関業者(フォワーダー )
5、その他社内の関係各部署
と最低限このくらいの関わりはあります。
1〜4は社外(会社規模によっては関連会社のところもあるでしょうが)です。一般的に「事務職」と聞くと社内の人たちだけとしか接する機会がない、社外の人とあまり関わることがない、と思われがちですが貿易事務に関しては社外との関わりが割と多いです。

また、企業によっては貿易事務兼営業事務の仕事も一緒に任されることもあります。
営業事務職もどの程度営業職のサポートを任されるか、その具合にもよりますが社外との関わりは多い方の職種です。
そのため貿易事務・営業事務をやっているとかなり様々な人と関わることになります。
有坂:私は貿易事務職と営業事務職を兼任するスタイルの会社で働いています。新卒の頃からその環境だったので最初の1年でかなり様々な社外の方々と接する、ということに慣れましたね。
社内の別部署で働いている事務職の方や友人で一般事務職をしている子などに話を聞くと
「電話の取り次ぎや来客対応以外で社外の人と会話することは一切ない」と聞いて、
仕事内容によって同じ内勤でもここまで違うものなんだな、と思ったことがあります。
実際に会わないからこそ身に付くコミュニケーション力
貿易事務職が仕事を進めていく上で様々な方と関わることを言いましたが
実際の関わり方は対面ではなく電話・メールがほとんどです。
有坂:企業によってはもしかしたらもっと便利なアプリやツールを使っているかもしれませんね。
貿易業界は「この書類の原本が必要」「直筆サインの入った本書が必要」「ARRIVAL NOTICEの連絡はFAXで」といったようなこともあるまだまだ古い部分がある業界なので、連絡も電話やメールがメインで使用されているところが多いのではないかと思います。
この電話やメールって一見するとコミュニケーション力必要無いと思いませんか。
おそらくですけど、逆です。
この貿易事務の仕事を10年以上してきて感じたのですが、
どんな仕事であっても対面より対面しない、
電話やメールなどのやりとりの方がコミュニケーション力ってかなり必要だと感じています。
特にメールはなおさらですね。
なぜなら、
・お互い顔も見ずに
・相手が今どんな状況かもわからず
・あれこれの仕事を「期日内にやってくれ」って頼む
ということしなければなりません。
改めて文字にして書いてみるとコミュニケーション力だいぶ必要だなと感じます。

これを聞くと
・人とあまり直接接することが苦手だから内勤がいいのに
・一般事務より専門性も身につくし長く続けられる仕事だと感じるけど、自分コミュ障気味だから無理かな
と思われる方もいるかもしれません。
しかしコミュニケーションをとることが苦手、という方も様々なタイプの方がいると思います。
実際に人と会って話すのが苦手なだけでメールなど文章でやりとりする分には大丈夫、など。
それとも電話もメールも全く知らない人とやりとりするのは無理、なのか。
よっぽど部屋にひきこもって誰とも会いたく無いレベルでなければ
最初の頃さえ少し緊張しても(誰だってそうですよね)徐々に電話やメールのやりとりには慣れてきます。
そして慣れてくるということは自然とコミュニケーション力も上がってきています。
自身のコミュニケーションとることの苦手度合いにもよりますが
多少様々な人と接することに苦手意識があっても貿易事務の仕事はできます。
なんなら業務を通じてコミュニケーション力を向上することもできます。
ベッタベタな昭和の営業マンみたいな人間関係を築く必要はない
コミュニケーション力と聞くと
・対人が大前提
・初対面の人とでも当たり障り無く適当に会話ができる
・そのまま仕事の話にうまくスムーズに突入できる
・なんならその勢いでそのままその日のうちに飲みに行っちゃう
のようなザ・昭和のサラリーマンみたいな、
リアルな世界での陽気なキャラクターの人物を思い浮かべてしまうかもしれません。
確かに仕事柄、このような性格の方の方が向いている仕事もあると思います。
ただ、こういったいかにも社交的全開なことが「=コミュニケーション力が高い」かといったら仕事においては必ずしもそうでは無いです。

貿易事務の仕事内容は一言で言うと
「無事に貨物を目的地に届けるための仕事の一端(主に書類業務)を担っている」です。
社内、社外問わず様々な人と関わりながら毎回1件の貨物を運び終えるというプロジェクトを小刻みに行なっているわけです。
ここで必要な「コミュニケーション力」は顧客を喜ばせたり、取引先と売買を成立させるために仲良くなるということとは違います。
いかに上手に仕事に関わる人にバトンパスをできるか、です。
このように聞くと
「所詮組織の歯車だ」
「直接売上や利益を出せるわけでも無いんだよな」
「既に販路が決まったものを決められたとおり運ぶ作業をするだけ」
などと思う方もいるかもしれません。
しかしそのおかげで
・自給率の低い日本で問題なく食料を購入することができたり、
・海外で作られた服やバック、飲食店などを楽しむことができたり、
と、日々人々は快適な暮らしを実現できています。
いつも普通に生活していると気付きにくいですが、
「上手に仕事に関わる人にバトンパスができている」おかげで、
普通に過ごせなくなった時にならないと気づけないくらい、現代人が快適だ!と思える生活の実現のために日々貢献しているのです。
世の中の人々がより快適に暮らすことに関われる仕事はとても誇りを持てる仕事だと思いますし、
そしてその仕事は必ずしも高い対人コミュニケーションを必要とする仕事ばかりでは無いのです。
どんな情報があれば相手がスムーズに仕事を取り組めるか考える
「いかに仕事に関わる人に上手にバトンパスができるか」を考える時にはバトンパスをする相手のことを考える必要があります。
私はメーカーで貿易事務をしています。
ここで輸入を例に出してお話ししていこうと思うのですが、
メーカーの貿易事務が貨物を輸入する案件で、関わる人たちにバトンパスをするというのは
基本的には船積書類の処理のことになります。
船積書類とは
invoice(請求書)
packing list(梱包明細書)
BL、SWB(船荷証券、海上運送上)
そのほかにcertificate of origin, health certificateや貨物によって必要になる書類などの総称として船積書類と言います。
輸出地から船積書類を入手し、
フォワーダーに通関依頼とともに船積書類を提出したり、
保税倉庫に貨物の入庫依頼をするとともに貨物の明細がわかる書類を連絡するなどをおこないます。
では、船積書類が来た段階でそれぞれ関係するところへ連絡すればそれで良いでしょうか。
貿易事務を始めたばかりの方はそれでも構わないです。
おそらく他の経験者の手助けもありつつ仕事を覚えている段階ですので基本的な仕事の仕方、流れを覚えるために船積書類が来た時点で行動するというのでも問題ないです。
(きっときちんとしている会社は仕事に穴があかないようちょいちょい裏でサポートしてます。結果いきなり大失敗して新人のせいにされるなんてことないでしょう。)
少しづつ仕事がどんなものか理解できた頃から
仕事を依頼するフォワーダー や倉庫の人がどうすればより仕事がしやすいか
と考えて仕事をしていくとスムーズなバトンパスができるようになります。
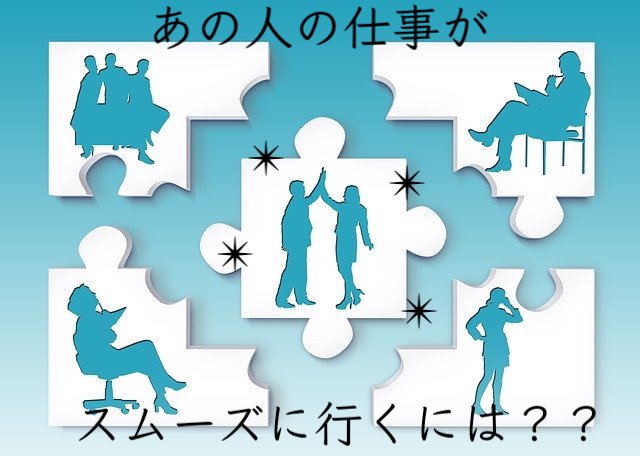
例えば
・船積書類が来る前にメールなどで得られる情報を得る→わかった時点で前もって関係各所に連絡をしておく
・検査が必要な貨物であれば→フォワーダーに前もって伝えておく、別途ほかに必要な書類がないか確認。
・検査の日程を確認し、逆算して販売に影響ないかを営業担当者に確認しておく、伝えておく。
・コンテナのサイズをあらかじめ伝えておく(コンテナヤードから倉庫に運ぶ際のトラック手配に必要な情報。コンテナno.もわかるとより良い)
・BLの内容に近しいものが少しでもわかるよう、booking information(船を予約した時の情報)の入手を試みる
など、ここに記載したのは一例で
貨物によっても前もってできること、できないこと、様々あると思います。
今自分の担当している貨物ではどんなことを確認して関連する人たちに伝えれば良いのか考えて実行してみることをお勧めします。
リレーのバトンパスと同じで
最初はあまりうまくいかないかなくても、練習すればだんだんスムーズにバトンを渡せるようになりますよね。
練習の中身は技術的な部分と、前走者と次走者のお互いの協力=コミュニケーション力の向上だと考えられます。
仕事でも同じです。
自分の仕事のその先の人のことを考えて仕事をすることでスムーズに仕事がすすみます。
相手も仕事しやすい人と仕事をする方が気持ちよく仕事ができますし人によっては少し融通をきかせてくれるようにもなります。
この時点で少しずつコミュニケーション力が徐々に身についてきていることもわかりますね。
先ほども言ったように、ベタベタな昭和のサラリーマンのような陽気なキャラで対人することだけがコミュニケーションをとる、ということではないです。
「あ、この人相手のことを考えてちょっとした情報もきちんと伝えてくれるんだな、気がきく人なんだな」
と思ってもらえたらそれは相手とコミュニケーションを取れている証拠です。
どんな時代になっても「信頼」が大事
コミュニケーションて聞くと目み見えての人付き合いのうまさみたいなと頃に目がいきがちです。
誰とでもすぐに話せていつも笑顔で明るい。みたいな。
しかしパッとみてわかりやすい行動だけがコミュニケーション力が高いわけではなく、
結果として「この人のこと信頼できるな」「この人と仕事するならなんとなく安心」と思ってもらえるような行動を淡々とコツコツとできることもコミュニケーション力と言えるのではないのでしょうか。
冒頭で
・事務職だったらそんな人と面と向かって関わることないしコミュニケーションとか必要?
・あまり社交的じゃないから事務職がいいと思っているんだけど
という質問を受けたことがあると言いました。
同じように感じている方がいたら
「自分はどんな形でコミュニケーションを仕事関係の人と築く事ができるだろう」と考えてみてください。
コミュニケーション=大勢の人とウェイウェイできる人だけと思っているならばそれは違います。
きっと「このような方法でならコミュニケーションを円滑にする事ができるかも」と思うものがあると思います。
そしてそれは、あくまで仕事をスムーズに進めるための方法でいいのです。
極端なことを言ってしまえば、友達を作るわけではありませんので。
(仕事をしているうちに結果仲良くなれたならそれはとても良いことだと思います)

職場の環境も大事ですね。
きちんと仕事を行なっているのに、
なんとなく静か、
人と明るく話せない、
といっただけで良くないように言われるようであれば辛いですよね。
そういった職場は「仕事」で評価しているつもりが知らず知らずのうちに上司の好き嫌いで判断しているのかもしれません。
働く場所や同僚、上司などの雰囲気は実際に働いてみないと本当のところはわからないため難しいところもありますが
自分は自分なりのコミュニケーション方法を用いてきちんと仕事をしているにも関わらず、
目に見えてわかりやすいコミュニーケーションでしか良しとしない、という職場は居続けるかどうか一度考えたほうがいいかもしれません。
あまり無理をしてその場に合わせ続けていると疲れますし、合わせられずに辛辣な視線を浴びせられ続けるのもどんどんしんどくなってきてしまいます。
最後は「職場環境も」と、少し話が逸れてしまいましたが
今回は貿易事務の仕事にはコミュニケーションが必要、
でもそのコミュニケーションとはリア充の対人方法みたいなことだけではないですよ、というお話をしました。
少し長くなってしまいましたが
最後まで読んでいただきありがとうざいます。
ご参考になりましたら幸いです。